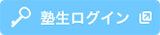「やればできる子だし、
やる気スイッチも押すんですが、
やる気が続かないんです。」
そんなご相談を受けることがありますが、
子ども達の“やる気”は、それを阻害する原因を取り除くことで継続します。
人には、人間としての理性と動物としての本能が共存しています。“やる気”が続かないのは、
“やる気”という理性が“生体恒常性”という本能に阻害されているということなんです。
「今日から勉強がんばるぞぉ!」という“やる気”は、昨日に比べて心が興奮状態にあることを意味します。
脳はこの状態を異常状態(平常ではない状態)にあると判断し、
生命と安全を維持するために異常状態を抑制させる指令を出します。
つまり、これが生体恒常性(ホメオスタシス)と呼ばれる本能です。
ある意味、“やる気”が一晩寝ると消えてしまうのは、しかたがないことなのです。
では、なぜゲームや自分の好きな事への“やる気”は継続できるのでしょうか?
それは子ども達の“やる気”の多くは、外部刺激によって喚起されるからです。
勉強に対する“やる気”もゲームに対する“やる気”も、
最初は誰かに言われたこと、何かを見たこと、友達に誘われたこと等から始まりますが、
同じ強さの刺激を継続すると感覚が麻痺し、刺激として受け止めなくなります。
(これもホメオスタシスです)
しかし、ゲームの場合は次から次と新たな展開があり、新たな刺激を受け続けることができます。
この刺激を与え続けられるゲームがヒット作になります。
しかし、勉強に対する刺激はどうでしょう?
新たな刺激どころか、子ども達は同じ事を耳にタコができるまで聞かされ続けてないでしょうか?
しかも、恐怖心を煽り逃げ出したくなるような刺激を与えていませんか?
では、どうすればいいのか
勉強とは、できなかったことができるようになる、本来ならば達成感や愉しさを体感できるものです。
そして、何より自分の夢や希望を実現するためのプロセスなのです。
子ども達への情報発信を間違わなければ、子ども達はワクワクしながらこのプロセスを愉しむことができます。
勉強という題材で“やる気”を自分でコントロールできるようになれば、
題材が就職であったり、資格であったり、どんなものでも対応が可能になります。
そんな自分力をつける指導が必要なんだと思います。