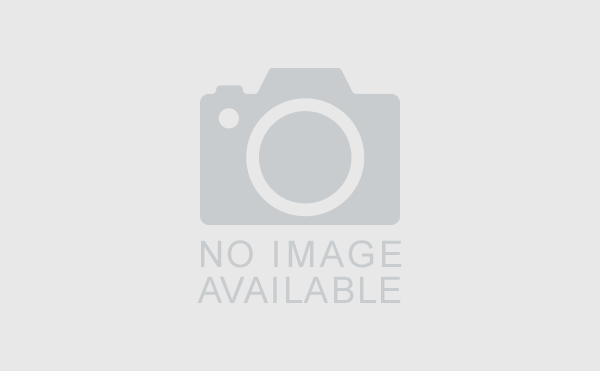高校入試 作文の書き方講座【第2回】〜テーマ設定と「構成メモ」の作り方〜
📝 高校入試 作文の書き方講座【第2回】〜テーマ設定と「構成メモ」の作り方〜
第1回では、合格作文の基本となる「3段構成」と「原稿用紙のルール」を学びました。これらは、良い作文を書くための「土台」です。
今回は、作文の出来を左右する「テーマ設定」と、書く前の準備である「構成メモの作り方」です。
この準備をしっかり行うことが、制限時間内に作文を書き上げるための最大のカギとなります!
- テーマを決める 〜与えられた課題から、「伝えたいこテーマ」を具体的にする〜
高校入試の作文では、「○○についてあなたの考えを述べなさい」といった抽象的な課題が出されることがあります。
この課題から、自分が伝えたい具体的なテーマを設定するステップが非常に重要です。
✅ ポイント1:話題は「一つ」に絞る
複数の主張やエピソードを盛り込もうとすると、一つ一つの内容が薄くなり、結局何を伝えたいのかが曖昧な作文になってしまいます。
- 課題例:「中学校生活で学んだこと」
- ❌(複数の話題)部活も勉強も委員会も頑張った。
- ⭕️(話題を一つに絞る)部活動で「継続することの大切さ」を学んだ。
このように、大きな課題から「これだ!」という一つの具体的なテーマに絞り込みましょう。
✅ ポイント2:「自分ならでは」の体験と結びつける
説得力のある作文には、あなたの考えを裏付ける具体的なエピソードが必要です。
テーマを選ぶ際は、「自分の実体験と結びつけやすいか」を基準に考えると良いでしょう。
- テーマ例:「努力の大切さ」
- 「努力は大事だ」と一般論を述べるだけでは響きません。
- → 部活の朝練を続けた結果、最後の大会で成功を収めた経験など、あなた自身が体験した「努力」を具体例に設定します。
- 書く前の準備:「構成メモ」で道筋を作る!
テーマを決めたら、すぐに書き始めるのは危険です!必ず5〜10分時間を使い、「構成メモ」を作りましょう。
これは、作文の設計図です。設計図なしに家を建てると、途中で材料が足りなくなったり、バランスが悪くなったりしますよね?作文も同じです。
| 構成メモに書くこと | 役割(3段構成との対応) | 実際のメモの例 |
| 主張(結論) | 序論 | 「困難に立ち向かうには、仲間の協力が不可欠だ。」 |
| 理由・根拠 | 本論 | 「一人で解決しようとしたが失敗。チームで役割分担したことで、目標達成できた。」 |
| 具体的なエピソード | 本論 | 「中学最後の文化祭での劇制作。大道具でトラブル発生 → 仲間と徹夜で作業 → 成功して団結力を実感。」 |
| まとめ/今後の抱負 | 結論 | 「この経験を生かし、高校でも周囲と協力しながら課題に取り組みたい。」 |
✨ 構成メモのメリット
① 時間短縮:一度流れを決めてしまえば、後はメモに沿って書くだけなので、途中で手が止まることがなくなります。
② 論理性の確保:序論と結論が一致しているか、エピソードが主張の裏付けになっているかを、書き始める前にチェックできます。
③ 字数調整の目安:全体の字数の何割を本論のエピソードに使うかなど、おおよその配分を考えておくと、字数オーバーや不足を防げます。
- 【実践】具体的なエピソードの書き方
構成メモができたら、いよいよ文章化です。特に本論で使う具体的なエピソードは、読み手の共感を呼ぶために最も力を入れるべき部分です。
- ただの報告で終わらせない:「〜しました。楽しかったです。」
- 「心の動き」と「学び」を加える:「〜という問題に直面し、最初は戸惑った。しかし、仲間の言葉で奮起し、解決策を見つけた。この経験から、諦めないことの大切さを学んだ。」
エピソードの中にあなたの感情や、その経験から何を得たのかを盛り込むことで、文章に深みが生まれ、説得力が格段に向上します。
次回は、いよいよ文章表現のテクニックに入ります。「伝わる文章」を書くための主語と述語のチェックや、語彙力アップのポイントを解説します。お楽しみに!