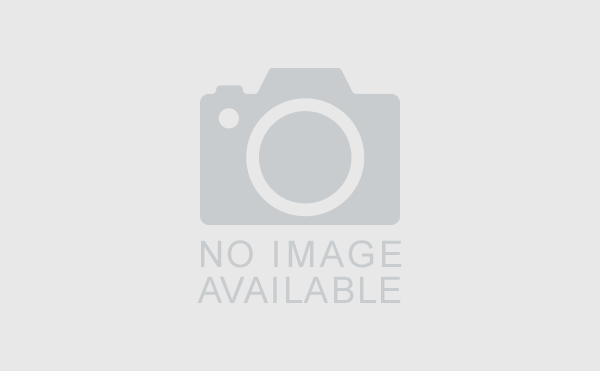高校入試 作文の書き方講座【第3回】〜「伝わる文章」のための表現チェック〜
📝 高校入試 作文の書き方講座【第3回】〜「伝わる文章」のための表現チェック〜
第1回では「構成」、第2回では「テーマ設定と構成メモ」と、作文の土台作りを解説しました。
今回は、いよいよ「文章表現」の質を高め、「正確さ」で減点を防ぐためのテクニックを学びます。
せっかく良いテーマと構成で書き進めても、文章が分かりにくかったり、文法ミスがあったりすると、評価は下がってしまいます。
「伝わる文章」を書くための最終チェックポイントを確認しましょう!
- 読みやすさの基本:主語と述語を整える
作文で最も陥りやすいミスが、主語(誰が/何が)と述語(どうした/どんなだ)の関係が曖昧になることです。
✅ ポイント1:一文を短くする
一文が長すぎると、主語と述語の関係がねじれたり、何を言いたいのかが分かりにくくなります。
- 悪い例:私は、部活動で苦しい練習に耐え、仲間と協力しながら目標に向かって努力し続けた結果、最後の大会で大きな成長を実感することができました。
- (主語「私」に対する述語が遠い)
- 良い例:私は、部活動で苦しい練習に耐えました。仲間と協力しながら目標に向かって努力し続けた結果、最後の大会で大きな成長を実感することができました。
- (適切な場所で句点(。)を打ち、文を区切る)
一文は、原稿用紙の2〜3行(40字〜60字程度)を目安にしましょう。
✅ ポイント2:主語と述語が対応しているか確認する
文章が長くなると、主語と述語がちぐはぐになってしまうことがあります。
- 誤った例:「私の将来の夢は、高校でボランティア活動を頑張りたいです。」
- (「夢は」と「たいです」がつながらない)
- 正しい例:「私の将来の夢は、高校でボランティア活動をすることです。」
- または:「私は、高校でボランティア活動を頑張りたいです。」
✅ ポイント3:「指示語」の多用を避ける
これ、それ、あれといった指示語を使いすぎると、何を指しているのかが曖昧になり、読み手に混乱を与えます。
- 指示語を使う際は、直前に具体的な言葉で説明しましょう。
- 正確さを追求!減点を防ぐ文法・表現のルール
入試作文は、あなたの「国語力」も評価されています。細かい表現ミスで減点されないように注意しましょう。
| ルール | 内容 | 悪い例 | 良い例 |
| 文体の統一 | 「だ・である」か「です・ます」のどちらか一方に統一する。 | 私は賛成だ。なぜなら〜だからです。 | 私は賛成だ。なぜなら〜だからだ。 / 私は賛成です。なぜなら〜だからです。 |
| 話し言葉の禁止 | 書き言葉を使い、友達との会話のような表現は避ける。 | やっぱり、努力はマジで大事だけど… | やはり、努力は非常に大事ですが… |
| ら抜き言葉の禁止 | 正しい五段活用を使う。 | 友達に会えれる(会える)。 | 友達に会える(会える)。 |
| 重複表現の禁止 | 同じ意味の言葉や表現を繰り返さない。 | まず最初に、私は〜 | まず、私は〜 / 最初に、私は〜 |
| あいまいな表現 | 主張する部分は断定的に書く。 | 〜かもしれない、〜と思う。 | 〜だ、〜と言い切れる。 |
- 見直しこそが「合格点」への近道!
すべての文章を書き終えたら、制限時間の中で必ず5分以上の見直し時間を確保しましょう。見直しは、書いた文章を客観的な読み手になったつもりでチェックする作業です。
最終チェックリスト
| チェック項目 | 内容 |
| 構成 | 序論と結論の主張が一致しているか。本論の具体例が主張の裏付けになっているか。 |
| 設問の条件 | 字数制限(9割以上か)、題名や氏名の有無など、問題の指示をすべて守れているか。 |
| 表記ルール | 原稿用紙の正しい使い方(行頭の空け方、句読点の処理)ができているか。 |
| 文法・表現 | 主語と述語が対応しているか。誤字脱字や文法の誤りはないか。 |
| 文体の統一 | 「です・ます」か「だ・である」が混ざっていないか。 |
このチェックリストを完璧にクリアすれば、あなたの作文は入試で求められる十分なレベルに達しています。自信を持って提出しましょう!
これで作文の基礎講座は終了です。
この3回で学んだ「型」「準備」「表現」の全てを、過去問などを使いながらしっかり練習し、公立高校選抜試験で成果を出せるよう頑張りましょう!